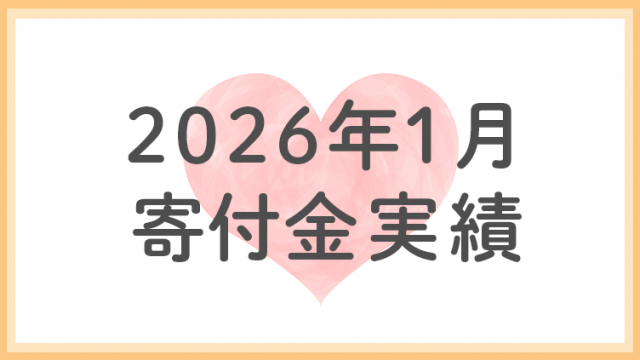洋服やぬいぐるみなど、不用品で寄付する方法を紹介。

近年はSDGs(持続可能な開発目標)が注目されており、リユース、エコなどの取り組みが各お店で行われるようになりました。また、個人が中古店やフリマアプリにて不用品を売ったり、リサイクル品を買ったりすることも目立っています。
そんな中で
「断捨離で出てきた不用品で社会貢献してみたい」
「なぜ不用品が寄付につながるの?その仕組みは?」
「モノで寄付するとき何に気をつければいいのだろう…」など、
物品での寄付でさまざま疑問を抱える方もいることと思います。また、必要でないとわかっていても「ゴミで捨てるにはもったいない」「手間をかけてまでお金には換えたくないと感じる場面」もあることでしょう。
当記事では不用品と寄付の繋がりや、要らないもので寄付する手順など「モノの寄付」にまつわる疑問を、実際にモノで寄付できる「モノドネ(monodone)」が詳しく解説します。
合わせて物品の寄付ができる団体・サービスも紹介していますので、寄付先の参考にしてください。
目次
- 不用品が寄付できるのはなぜ?
・不用品寄付のメリットとは?
・寄付の使い道
- モノそのものを寄付する方法
・寄付できるモノとは?
・物品を受け付けている場所
- モノをお金に換えて寄付する方法
・モノで寄付するための「3つの型」
・寄付金に換えられるモノ
・不用品を寄付できる団体・サービス
- 不用品を寄付するときの注意点
- まとめ
1.不用品が寄付できるのはなぜ?
「不用品の寄付」と言われても、具体的にイメージしづらい方もいると思います。
不用品の寄付とは「要らなくなったモノを必要とする人に届ける行為」です。この不用品の寄付が成り立つ背景には「国の格差」が密接に関わっています。
世界には「先進国」と呼ばれる国と、「開発途上国(または発展途上国)」と呼ばれる国があります。
先進国とは、簡単にいうと「経済が大きく進んでおり、国民の生活水準が高い国」を指します。たとえば生活するために必要なガス・電気・水道・道路・公共施設などのインフラ設備は、国の格差を計る項目の一つです。そして私たちが生活する日本は、他国と比べるとインフラ設備が整った国とも言えます。
一方で、日本の廃棄物の量をご存知でしょうか。
環境省が発表したデータによると、日本では年間「4,274万トン」ものゴミが出ています。東京ドームで換算すると「約115杯分」です。このゴミには食品ゴミだけでなく、衣類や日用品も含まれます。
この、日本の一般家庭で出る不用品の大半は、国が変われば「まだまだ使えるモノ」なのです。しかしゴミに分別されてしまえばモノの価値は失われ、さらには環境にも悪影響を及ぼします。
このような廃棄物問題の背景から、日本でモノの寄付を募集している団体では、貧困民が多く暮らす国やインフラが不十分な国などに対し、物資による支援活動をしています。
またSDGsの12番目には「つくる責任・つかう責任」といった目標が掲げられています。食品でも家電でも、寄付、またはリユースすることでゴミとしてではなく、「必要なモノ」として「必要としている人」の手に渡ります。
そして家庭ゴミの排出量が減少することで、地球温暖化の原因の一つである「二酸化炭素(Co2)」の発生を抑え、環境保全への貢献も期待できるでしょう。
不用品寄付のメリットとは?
モノを売ったり寄付したりする場合、少なからず手間は発生します。しかしモノを売る場合、副収入が得られる、売ったお金で新しいものが買える、貯金ができるなどのメリットも得られます。では一方で、不用品寄付をおこなった場合は一体どんなメリットが考えられるでしょうか。
寄付者に対するメリットは、大きく3つが挙げられます。
| ・環境保全への貢献 ・社会貢献に参加できる ・不用なモノが片付けられる |
環境保全への貢献
不用品寄付は、環境保全へ貢献することにもつながります。
不用品を寄付してゴミを減らせば、ゴミを焼却するときに発生する二酸化炭素が減らせるからです。
日本では、2020年度の二酸化炭素の排出量は10億6,400万トンとなり、2013年度と比べると19.2%減少しています。
環境省HP:https://www.env.go.jp/content/000128750.pdf
しかし、日本の二酸化炭素排出量は世界5位となっており、環境問題を悪化させないためにも、さらに二酸化炭素排出量を減らす必要があります。
そして私たちが二酸化炭素を減らすためにできる身近なことの一つが「ゴミを減らすこと」です。ゴミの焼却のうち家庭ゴミの割合は約12%を占めており、意識してゴミを減らせば二酸化炭素排出量削減につながるでしょう。
普段からゴミを捨てるときに分別をしたり、エコバッグやマイボトルを持ち歩いたりと、ゴミを減らす努力をしている方も多いはずです。
そこで、不用品も寄付してゴミを減らすとなるとどうでしょう。小さな積み重ねですが、かなりのゴミの量を減らせます。
本来ゴミとして捨てるはずだった不用品を寄付し、必要な人のもとで活用されることで、ゴミにはなりません。
ゴミを減らすことで二酸化炭素の排出量削減につながり、地球環境の保全へとなるのです。
社会貢献に参加できる
不用品を寄付することで「社会貢献」に参加できます。
実際に社会貢献しようと思っても、これまで行動に移せなかった人も中にはいるかもしれません。
具体的には「リサイクル(リユース)する」「ゴミを減らす」「届けた先を少しでも豊かにする」などがあげられます。
また金銭での寄付に対してハードルを感じていた方にも、不用品寄付は「誰でも始めやすい社会貢献のカタチ」と言えるでしょう。
不用なモノが片付けられる
不用品寄付を行うことで、家の要らないモノを片付けることができます。
断捨離や片付けをする際に「どこに売ろうか」「捨てる?売る?」などで迷ったことはありませんか?まだまだ使えるものでも、日用品や雑貨、おもちゃなどで「売るにはちょっと…」と処分に困ることも少なくないでしょう。
不用品の寄付は、家の片付けと社会貢献を一緒におこなうことができます。後半では寄付サービスの選び方なども合わせて紹介していますので、ご自身にあった寄付を検討してみてください。
| ※デメリットは、3章の「モノをお金に換えて寄付する方法」で種類別に解説しています。 |
寄付の使い道
不用品を用いた寄付には、「モノ自体を直接、開発途上国に支援」する活動と、「寄付金で支援」する活動の2つに分けられます。
モノ自体を送る支援はイメージもわきやすい一方で、後者の寄付金で支援する活動では「寄付金の使い道」も気になるところだと思います。
物品の寄付を受け付ける団体の取り組みは、おもに海外支援と社会貢献活動です。
海外支援
海外支援には、「貧困民や恵まれない子ども・大人たちがいる、開発途上国を中心とした国際活動」があります。
開発途上国では、日本と比べると著しく深刻な社会問題を抱えるケースも少なくありません。
たとえば貧困であれば、「1日1.9ドル未満」で暮らす人は世界で7億3600万人いますが、その多くは開発途上国の人びとです。また紛争、元子ども兵、女の子の早すぎる結婚・妊娠なども、日本ではあまり聞きなれません。
支援団体では、こうした開発途上国が抱えるさまざまな問題解決のために寄付金を使っています。
国内の社会貢献活動
私たちの身近にも解決しなければならない社会問題は数多くあり、国や団体を通じてさまざまな支援が行われています。代表的なものとして、貧困問題、介護問題、ジェンダー不平等、路上生活者、少子高齢化、フードロスなどがあげられます。たとえば日本の貧困問題でいうと、ひとり親の子ども・その家族へ支援する取り組みは多いです。寄付金は「貧困家庭への生活支援」や「施設の運営費」、「進学のための奨学金」などに充てられています。
2.モノそのものを寄付する方法
大切に使用してきた洋服や、子どもの成長を見守ってきたぬいぐるみなどを手放す決断をしたものの「できればゴミにしたくない」。でも、「リユースショップに行くのも面倒」ということもあるかと思います。
ここでは洋服やぬいぐるみなど、不用品そのもので寄付する方法をご紹介します。
不用品をそのまま寄付したい場合は、今手元にあるモノを受け付けてくれる団体を探す必要があります。それは支援団体ごとで、受け付けできる品物が異なるためです。
寄付できるモノ
現在、日本にある「物品の受付をおこなう支援団体」を見てみると、洋服やぬいぐるみ以外にも、さまざまなモノの寄付を受け付けていることが確認できます。
| ジャンル | 具体例 |
|---|---|
| 衣類 | 汚れやダメージのない古着、男性用の防寒着、未使用のパジャマなど |
| ぬいぐるみ | アニメ・ゲームキャラクター、アミューズメントパーク(ディズニー・USJなど)、UFOキャッチャーの景品 |
| おもちゃ | 男児・女児の玩具、ミニカー、プラモデル、ボードゲーム、レゴ、戦隊フィギュアなど |
| 日用品・雑貨 | タオル、懐中電灯、ランドセル、食器類、絵本、椅子など |
| ブランド品 | バッグ、財布、アクセサリーなど |
| 貴金属 | 地金、金製品(K18、K14等)、プラチナなど |
| 家電 | デジタル家電(デジカメ、オーディオ、パソコン等)、生活家電(電子レンジ、ドライヤー、ホットプレート等)など |
| 金券 | 全国百貨店共通券、旅行券、テレホンカード、切手、ハガキなど |
| 趣味嗜好 | カメラ・お酒(ブランデー、ウイスキー、日本酒、缶チューハイなど) |
| 書籍 | 絵本、参考書、辞書、漫画 |
| 食品 | お米、飲料(水・ジュースなど)、缶詰、インスタント・レトルト食品、調味料、乾物など(すべて賞味期限が1ヶ月〜3ヶ月以上※団体による) |
| ペット関連 | ドッグフード、シーツ |
表でも分かる通り、品物によっては条件があります。
たとえば洋服や雑貨なら「汚れやシミのないもの」「一部雑貨は未使用のみ」などとするほか、食品なら、「賞味期限が1ヶ月〜3ヶ月以上先のもの」が一般的となっています。
物品寄付を受け付けている場所
モノでの寄付を受け付けている場所をいくつかご紹介します。
NPO
現在、数多くのNPOが物品寄付を受け付けています。
NPOとは「営利を目的とせず、社会課題の解決のために活動する組織」です。
現在、日本には約5万以上のNPOが存在しており、福祉、子ども、災害、環境、食べ物と、その活動内容は多岐に渡ります。また受け付ける品物は、団体の活動に関連した品であることが多いです。
まずは一度、自分が興味ある分野の団体が物品寄付をおこなうか調べてみるのも一つです
福祉施設
児童養護施設、障害者施設、老人ホームなどの福祉施設にも寄付できます。
児童養護施設であれば、家電製品、おもちゃ、書籍、衣類、自転車など。
また障害者施設や老人ホームなら、タオル、車椅子、衛生用品(マスク、消毒液等)、デジタル機器(パソコン、タブレット)、絵の具や色画用紙などの文具類などが、一般的に喜ばれやすい品目となっています。
公共機関
公共機関にも寄付できます。
各種学校、幼稚園、保育園、図書館などがそれにあたります。図書館は、絵本や文学書などの書籍を中心とした寄付です。
また、一部の病院でも物品を受け付けている場合があります(現在は新型コロナウイルスの観点から、受け入れ中止)。
行政機関
地方自治体、動物愛護センター、ボランティアセンターなど、行政機関にて物品の寄付を受け付けるケースもあります。ただし地方自治体では、個人だと受け入れ不可となる可能性があります。
動物愛護センターでは、ペットフードやペットシーツなどを寄付すると喜ばれます。
動物に関わる活動に興味がある方は、下記の動物愛護の取り組みをまとめた記事をご参考ください。
>>動物愛護・保護団体のお仕事って?どんな活動をしているの?その取り組みをご紹介します
物品寄付の流れ
モノそのものを寄付した場合の流れを、洋服とぬいぐるみを例にご紹介します。
洋服を寄付する
洋服を寄付し、社会に役立てる取り組みはいくつかあります。
その一例として「古着deワクチン」は、専用回収キットを購入し洋服やバックを送ることで、社会に役立てる仕組みです。集まった洋服やバックは主に開発途上国で再販され、現地の雇用創出につなげられています。
ぬいぐるみを寄付する
ぬいぐるみの寄付を受け付けている団体はいくつかあります。
代表的な団体は、下記があります。
- 国際子供友好協会
- ワールドギフト
寄付されたぬいぐるみは、国内外の児童福祉施設や学習施設に届けられます。
寄付するモノの送り方としては各団体が募集しているモノを元払いで送る方法が一般的ですが、ぜひ各団体のHPをご参照ください。
物品寄付はそのときどきの社会状況によって受け付ける品目が変わったり、送り方が変更になったりすることがあります。
一つの具体例としては「衣類」です。衣類は、数年前まで数多くの団体が受付をおこなっていました。しかし2020年のコロナウイルスの影響から「海外への輸出」が難しくなり、一時的に受け付けを中止する団体が急増。衣類の引取は、支援団体だけでなくリユースショップにも影響が及びました。
物品寄付できる団体をまとめたサイト等では、一部の情報が古くなっている可能性もあります。間違って送ると団体に迷惑をかけてしまう恐れがありますので、利用する際は各団体のHPを参照し、最新情報を得るようにしましょう。
3.モノをお金に換えて寄付する方法
続いては「モノをお金に換えて寄付」する流れを見てみましょう。
実際に、不用品をお金に換金して寄付したいと思っても、やり方や送れるものが分からない方も多いと思います。
せっかく支援団体を活用するのであれば、なるべく無駄を省いてスムーズに終わらせたいですよね。
ここでは不用品を用いてお金の寄付をする方法から、お金に換えられる品物を詳しく解説したいと思います。
モノで寄付するための「3つの型」
まずは「どうやってお金に変えて寄付するのか」ですが、大きく3つの方法が挙げられます。
| 1.買取金額をそのまま寄付する「買取型」 2.自分で売却してから寄付する「自発型」 3.不用品を梱包・発送して寄付する「提供型」 |
1. 買取金額をそのまま寄付(買取型)
一つ目は、支援団体と提携する買取りサービスで品物を買い取ってもらい、査定金額をそのまま団体に寄付する方法です。ここでは「買取型」とします。
買取型のメリットは、寄付までの流れが「シンプル」なことです。一般的に寄付できる買取りサービスは、社会貢献に取り組む団体と提携しています。たとえば本サイトの「モノドネ」もその一つです。
モノドネは、リユース事業を行う「買取王国」が運営しており、洋服やおもちゃなど、さまざまな品目を売ることができます。
2. 自分で売却してから寄付(自発型)
2つ目は、好きな方法で不用品をお金に変えてから、団体に寄付する方法です。
ここでは「自発型」とします。
自発型の特徴は、やり方次第で「すこしでも高い金額が期待できる」こと。少しでも多くのお金を寄付したい場合は一つの選択肢です。たとえばフリマアプリの「メルカリ(mercari)」や「ペイペイフリマ(PayPay)」、また「ヤフオク(Yahoo!)」などのオークションサービスを使うと、買取りよりも高い値がつく場合もあります。
一方、自発型では「手間」「時間」を要するため注意が必要です。購入者とのやりとり、取引時のトラブルなどがそれにあたります。また買取型なら査定してそのまま寄付の手続きが行なえますが、この自発型では、あらためて寄付先や寄付サービスを選ばなければならない手順が発生します。
売却する目的が「不用品で社会貢献に参加したい」「支援団体を応援したい」といった場合は、1つ目に紹介した買取型、もしくは3つ目に紹介する提供型を検討してみましょう。
3. 不用品を梱包・発送して寄付(提供型)
3つ目が、団体やサービスに不用品を送るだけで、その品物自体を必要とする人に直接届いたり、団体がお金に換えて活用したりする方法です。ここでは「提供型」とします。
提供型の仕組み
- 送りたい品をダンボールに詰める
- 団体へ送る
- モノが支援団体に寄付され、団体に活用される
提供型はひとつ目の買取型と似ていますが、両者の大きな違いは「品物を査定するタイミング」です。
買取型ではモノでの寄付を募っているサービスが査定し、提供型の場合は「別の買取りサービス」で査定を行うのが一般的です。そして提供型は送られてきた寄付品すべてを換金するとは限らない(モノそのものを直接届ける場合もある)ため、もし換金したとしてもその金額を寄付者は知れない場合がほとんどです。
提供型は、あくまでも寄付に特化したサービスという点が大きな特徴のため、不用品で寄付を始めたい人には「無駄のない方法」といえます。一方で、リユースショップの買取査定と同じように「査定金額(=寄付金額)を正確に知りたい」という場合は、買取型を選ぶのが良いでしょう。
3つ型のメリット・デメリット比較表
| 寄付の方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 買取型 | ・寄付までの流れがスムーズ ・査定のプロが在籍するので安心 | ・フリマアプリと比べて安くなる品物もある ・送料やキャンセルなどの規約を読む必要あり |
| 自発型 | ・品物によっては、高く売れるケースもある ・自由度が高い | ・手間と時間がかかる ・アプリを使うことで、本来の趣旨とズレる可能性も(余計なものを見る・買うなど) |
| 提供型 | ・3つの中では最も「単純」かつ「寄付に特化」している ・まとめて引き取ってもらえやすい | ・一律での寄付(提供)のため、モノとしての活用か、換金されるかは団体によって異なり、多くの場合寄付者がそれを選ぶことは出来ない。 |
寄付金に換えられるモノ
続いて「寄付金に換えられるモノ」を見ていきましょう。
寄付金に変えられるモノは、これまでと同じく支援団体によって異なります。たとえば「洋服やぬいぐるみなどの品物を受け付ける団体」から、「本だけに特化したサービス」など、その団体の活動方針によって決められています。
また「モノでの寄付」と同様に品物ごとに条件を指定するケースもあるため、事前に団体ごとの利用方法を確認するなどの注意は必要です。
| ジャンル | 寄付の方法 |
|---|---|
| 衣類 | ・買取型(サービスで売って寄付) ・自発型(好きな方法で売却・寄付) ・提供型(郵送して団体に寄付) |
| ぬいぐるみ | |
| おもちゃ | |
| 日用品・雑貨 | |
| ブランド品 | |
| 貴金属 | |
| 家電 | |
| 金券 | |
| 趣味嗜好 | |
| 書籍 | |
| 食品 | 基本的に「提供型」のみ |
| ペット関連 |
洋服・おもちゃ・家電などの品は、買取型や自発型などで一度換金し、好きな団体へ寄付することも可能です。一方で、食品の場合は「受付団体への寄付」のみがほとんどですので、その点の違いも理解しておきましょう。
不用品を寄付できる団体・サービス
不要なものを寄付する方法、寄付できるものを見てきた中で、「実際にどのサービスを使って寄付すればいいのだろう」と迷う方もいらっしゃると思います。
そこで過去の実績や事例を踏まえ、モノの寄付を受け付けている支援団体・サービスを5つ紹介します。
セカンドライフ
セカンドライフは「認定NPO法人グッドライフ」が運営しています。不要品とされる物資を必要とする人々に寄付として届けることで、国内外の人々に笑顔を届けています。また、寄付された物資のその後を写真や文章でレポートし、「寄付の見える化」に尽力しています。寄付できる物資も、古着やぬいぐるみ、ランドセルや文房具、絵本や生活雑貨など多岐に渡ります。また寄付1箱に付き2件のワクチンが途上国に送られます。
>>セカンドライフを詳しく見る
いいことシップ
いいことシップは、不用品寄付で子どもたちを支援する団体です。定期的な寄付報告に踏まえて、ウェブメディアでも掲載された実績を持ちます。衣料品やぬいぐるみはもちろん、工具や家具などの他サービスでは扱いづらい品目が寄付できるのも特徴。「ユニセフ」や「日本赤十字社」などを含む10つ以上の寄付先から選ぶことができます。
>>いいことシップを詳しく見る
エコトレーディング
エコトレーディングは「株式会社ウォーク」が運営する、不用品寄付を通じて社会貢献に繋げるためのサービスです。衣類、ランドセル、ぬいぐるみ、文房具、ベビー用品などを受け付けており、国内外問わず「新しい持ち主」のもとへ届ける活動を行っています。収益金の一部は、被災地復興のため、国内の児童養護施設、ボランティア活動などにも活用されます。
>>エコトレーディングを詳しく見る
ワールドギフト
ワールドギフトは、物品寄付を中心とし、開発途上国に向けて食糧・医療支援をおこなう民間の非営利団体です。衣類、おもちゃ、キッチン用品、バッグ、文具など、さまざまものが寄付可能です。アフリカ大陸などを含め、これまで92カ国に対して支援を繰り返した実績を持ちます。
>>ワールドギフトを詳しく見る
チャリボン
チャリボンは、バリューブックスが運営する「古本で寄付」ができるサービスです。チャリボンは査定サービスと寄付の一体型のため、金額は品物の量ではなく「価値」に応じて変動します。書籍の他にも、DVDやアルバムCD、ゲームなども対象です。また値段がつかない場合でも、一部の公共施設、福祉施設、古紙回収業者に引き渡しをおこなっています。
2010年以前に出版された古い本、不揃いの漫画セットなど、一部値段がつかない品もあります。
>>チャリボンを詳しく見る
モノドネ
モノドネは「株式会社買取王国」が運営する、「モノと寄付をかけ合わせたサービス」です。買取王国は、古着やブランド品、おもちゃ、ゲームなどを買取り・販売するお店で、モノドネはその査定サービスを活用し、社会貢献につなげるための取り組みをおこなっています。プロの査定員が一点ずつ見積もりするため、品物によっては高額の寄付もできます。
現在モノドネでは、ブランド品、時計、デジタル家電、カメラ、テレカ・切手等の金券類、おもちゃ、お酒、骨董品、本、衣類など、幅広い品目を取り扱っています。
>>モノドネを詳しく見る
4.不用品を寄付するときの注意点
不用品を寄付する際に、あらかじめ注意すべき点があります。
それが以下の3つです。
| 1.寄付できる状態 2.事前確認 3.送料負担 |
1.寄付できる状態
不用品を寄付する場合、使える状態について考慮する必要があります。
いくら「使える」と思うものでも「需要」がなければ意味がないためです。
一つの指標として、
| ・壊れていない ・リユースショップ、フリマやバザーで販売されている状態 |
を目安にしてみてください。
不用品寄付をおこなう際に「自分がこれを受け取ったら嬉しいか」「その品を誰が使うのか」を意識すると、どんなものだと支援者や団体に喜ばれるのか理解しやすいでしょう。
2.事前確認
不用品寄付をおこなう場合に、事前確認が必要な場合もあります。
「こんなものを寄付してもよいか」「現在、物品の寄付をおこなっているか」と、団体に前もって確認を取ります。
もし事前確認なしで送ると、寄付先と支援者それぞれに以下のトラブルが発生する可能性もあります。
| ・想定していない廃棄物の分別が発生する(寄付先) ・返送の際に返送料がかかるケースがある(支援者) |
中には回収業者に引き渡す団体もありますが、少しでも迷惑にならないよう、基本的には何が送れるのか事前に把握した上で物品寄付を活用しましょう。
3.送料負担
3つ目が「送料負担」です。
支援団体が行う不用品の寄付は、寄付者が送料を負担するケースがほとんどです。送料は、配送業者やダンボールの大きさにもよりますが、1つ1,000〜2,000円は発生します。「なぜ送料を負担しないといけないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
物品寄付が元払いである大きな理由として、「支援するまでの手間・コストの発生」があげられます。
具体的には以下のものです。
届いたモノを分類するための手間
支援者から届いたものは、最初に「分別」の工程が発生します。
分別は、団体が取り扱う種類でも異なります。たとえば洋服なら大人用と子ども用、食品なら賞味期限ごと・種類ごとに細かく分類。
そして分別には人手が必要で、人件費が発生します。
NPOなどの非営利組織ではボランティアも多いですが、お金をいただいて働く正社員・従業員もいます。
寄付品を保管するための管理費用
寄付された品を分類したあとは、管理が必要です。新たな人へ届けるまでに、痛みが発生したり、壊れたりしてしまっては本末転倒ですよね。
管理するには、保管場所や光熱費などが発生します。また食品ともなれば、支援を受ける方の衛生面も考慮しなければなりません。
品物を海外に送るための輸送費用
開発途上国など「海外への支援」をおこなう場合、品物を輸送するための費用も必要です。基本的には、一定の個数に達したら、海外へ輸送します。
輸送費は「輸送先」によって異なりますが、決して安価な金額ではありません。場合によっては、寄付品とは別に輸送費を求める寄付団体もあるほどです。
各品物を寄付金にするための手間
当記事のパート2「モノそのもので寄付する方法」では、”物品寄付にはモノで支援する形と、寄付金に換えて支援する形の2種類がある”と解説しました。
後者の場合、寄付金に変えるための手間や手数料などが発生します。
たとえば金券・切手・はがきなどは、そのまま支援者には届きません。団体等が自ら換金し、そのお金を支援するための活動費、支援団体への寄付に充てています。
また換金する場合にも、1つ目の分別と同様に人件費などが発生します。
このように、物品寄付は団体が負担すべき費用が数多く存在します。
支援者が送料負担することで、困窮した大人・子どもたち、開発途上国が抱える課題の解決促進に、少しでも多くの寄付金を役立てることができているのです。
まとめ
今回は不用品を用いた寄付について、詳しくご紹介しました。
モノの寄付は誰でも気軽に始められるがゆえに、団体が決めたルールを無視しておこなわれるケースも少なくありません。
「要らないものが誰かのために役立つかもしれない」
こうした思いから参加できる不用品寄付は、立派な社会貢献の一つといえます。
ご家庭で要らないものを寄付される場合は、ぜひ団体の活動理念やルールを確認いただき、また寄付は「団体と寄付者が一丸となって支援している」ということも意識してみましょう。
モノドネでは、あなたの不用品を寄付金に変えることができる新しい仕組みです。
もう使わないけど捨てるにはもったいない。
そういったお品を寄付金に変えませんか?
手続きは3ステップ
-
寄付したい団体を選ぶ
モノドネ掲載団体の中から、あなたが応援したい活動団体を選びます。
-
申し込みをする
申し込みフォームに必要事項を入力し、完了メールを受け取る。
-
寄付品を発送する。
メールに記載された発送先へお品を発送する。
※買取王国系列店舗への持ち込みも可能です(一部対象外店舗あり)。
発送されたお品を専任スタッフが査定し、その査定額全額があなたの選んだ活動団体への寄付金になります。
査定額はメールにてお知らせします。
選んだ活動団体が寄付金控除対象団体であれば、寄付金控除を受けられます。

お品はそれを必要とする次の誰かにお繋ぎし、リユース・リサイクルされます
あなたにとっての不用品を、モノドネで社会に役立つお品に変えませんか?