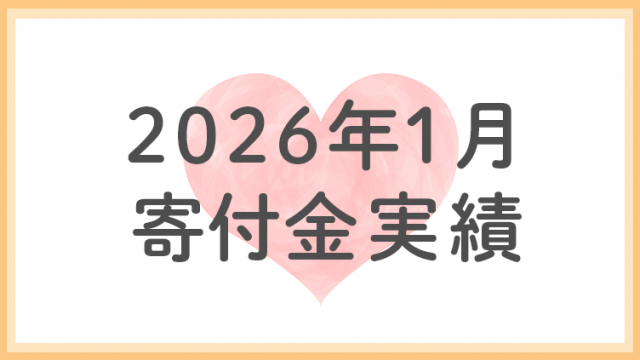社団法人とは?どんな活動をしているの?

社団法人は現在、その根拠となる法律によって「社団法人」「公益社団法人」「一般社団法人」の3つに分かれています。
本記事では社団法人について、またそれぞれの仕組みやその活動について紹介します。
社団法人とは
社団とは一定の目的のもとに集まった人の団体であり、社団法人とは法律によって法人格が与えられた法人をさします。
なお法人格とは、その団体名義で銀行口座を開設したり財産を所有したりすることができる法律上の人格のことです。
現在、社団法人という名称の法人格は設立できない
2008年に公益法人制度改革があり、大幅な法改正が行われました。これにより現在では、社団法人という名称の法人格を新たに設立することができなくなっています。
2008年の改革以前は、旧民法34条や特別法の規定に基づき「社団法人」という名称の法人が存在していました。
しかしながら、この制度には下記のような大きな問題がいくつもありました。
- 公益性の判断が、主務官庁の裁量によるところが多かった
- コネがなければ社団法人の設立が難しかった
- 官僚や政治家の天下り先になる事例が多かった
- 補助金などの不正支出問題などが多かった
公益法人制度改革では、これらの問題解決も目的の一つとされ2008年1月の新たな法律の施行からは「公益社団法人」「一般社団法人」の2つに区分されることになりました。
公益社団法人とは
公益社団法人とは、一般社団法人の中でも公益事業を主たる目的にしている法人のことです。公益社団法人になるためには、民間有識者から構成される第三者委員会で公益性の審査を経て、行政庁に認定される必要があります。
ここからは公益社団法人の
- 設立
- 活動(事業内容)
- 所得の課税対象
などについて紹介します。
公益社団法人を設立するには
公益社団法人を設立するためには、主務官庁より公益性を認められる必要があります。
基本的な設立の流れは、以下の通りです。
- 一般社団法人を設立する
- 一般社団法人において公益認定申請書を作成し、主務官庁へ提出
- 主務官庁より公益社団法人として問題がないことが認められると、公益認定確認書が発行される
- 一般社団法人が公益認定確認書をもって法務局を訪れ、公益社団法人への移行登記を行う
特に3の公益認定確認書の発行に際しては、民間有識者から構成される第三者委員会で公益性を認定されるステップを踏む必要があるなど、かなりの時間と労力が要される仕組みになっています。
公益認定を受けると公益社団法人という名称を使用することができるようになり、公益社団法人に対する寄付を行う個人や法人への税制上の優遇措置が受けられるようになります。
もちろん「暴力団員などが支配している」「滞納処分終了3年未満である」「認定取り消しから5年経過していない」などの欠格理由がある場合は、公益認定確認書は発行されず公益社団法人になることはできません。
公益社団法人の活動(事業内容)
公益社団法人が行う事業、すなわち公益目的事業とは学術や技術、慈善など不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであり、具体的には下記の23事業をいいます。
- 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
- 文化及び芸術の振興を目的とする事業
- 障害者もしくは生活困窮者または事故、災害もしくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
- 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
- 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
- 公衆衛生の向上を目的とする事業
- 児童または青少年の健全な育成を目的とする事業
- 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
- 教育、スポーツなどを通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、または豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
- 犯罪の防止または治安の維持を目的とする事業
- 事故または災害の防止を目的とする事業
- 人種、性別その他の事由による不当な差別または偏見の防止および根絶を目的とする事業
- 思想および良心の自由、信教の自由または表現の自由の尊重または養護を目的とする事業
- 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
- 国際相互理解の促進および開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
- 地球環境の保全または自然環境の保護および整備を目的とする事業
- 国土の利用、整備または保全を目的とする事業
- 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
- 公正かつ自由な経済活動の機会の確保および促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
- 国民生活に不可欠な物資、エネルギーなどの安定供給の確保を目的とする事業
- 一般消費者の利益の擁護または増進を目的とする事業
- 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として法令で定めるもの
上記は、「公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第2条の中で記されているものです。
参考:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 | e-Gov法令検索
公益社団法人の所得とその課税対象
上記に記載した公益目的事業23事業に関するものは非課税ですが、公益社団法人であっても収益事業から生じた所得は全て課税対象になります。
参考:公益法人などに対する課税に関する資料 : 財務省 (mof.go.jp)
一般社団法人とは
一般社団法人とは、「一般社団法人および一般財団法人における法律」を根拠に設立される非営利法人のことです。
ここからは一般社団法人の
- 設立
- 活動(事業内容)
- 所得の課税対象
についてみていきます。
一般社団法人を設立するには
一般社団法人は主務官庁の設立許可を必要としません。そのため法律に定められた要件を満たすことができれば、法務局への登記のみで設立することができます。
設立にあたって主務官庁より公益性が認められる必要がある公益社団法人とは、設立の段階から大きな違いがあります。
一般社団法人の活動(事業内容)
一般社団法人は非営利法人ではあるものの、公益性を求められておらず法人設立後に行政機関に監督されることもありません。
事業内容についても基本的には法人の自由であり、公序良俗に反しない限りはどのような事業を行うこともできます。株式会社のように収益のみを目的として事業を行うことも可能です。
ちなみに非営利法人とは、株式会社のように株主に利益の配当をしないという意味であり、利益を出してはいけないということではありません。よって非営利法人であっても利益を出すことは何ら問題なく、事業を行って得た利益は法人の活動費用に充てることができます。
活動という点でも、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する23の事業を行うことが前提とされた公益社団法人とは異なります。
一般社団法人の所得とその課税対象
一般社団法人では、通常は全ての所得が課税対象となります。
公益社団法人では収益事業の所得のみが課税対象となり、また公益社団法人への寄付者へも優遇措置がある一方で、一般社団法人は、寄付金も売上として計上されるため課税対象となります。
しかし、税制上の優遇がある非営利型法人の要件を満たす一般社団法人の場合は、「収益事業から生じた所得についてのみ課税」されるため、寄付金収入は課税の対象外です。
まとめ
今回は、社団法人・公益社団法人・一般社団法人について紹介しました。
似たような名称ではあるものの、それぞれ設立の仕組みや事業内容はそれぞれ大きく違います。もちろん、それに伴い社会での役割なども異なります。ぜひ参考にしていただければ幸いです。
モノドネでは、あなたの不用品を寄付金に変えることができる新しい仕組みです。
もう使わないけど捨てるにはもったいない。
そういったお品を寄付金に変えませんか?
手続きは3ステップ
-
寄付したい団体を選ぶ
モノドネ掲載団体の中から、あなたが応援したい活動団体を選びます。
-
申し込みをする
申し込みフォームに必要事項を入力し、完了メールを受け取る。
-
寄付品を発送する。
メールに記載された発送先へお品を発送する。
※買取王国系列店舗への持ち込みも可能です(一部対象外店舗あり)。
発送されたお品を専任スタッフが査定し、その査定額全額があなたの選んだ活動団体への寄付金になります。
査定額はメールにてお知らせします。
選んだ活動団体が寄付金控除対象団体であれば、寄付金控除を受けられます。

お品はそれを必要とする次の誰かにお繋ぎし、リユース・リサイクルされます
あなたにとっての不用品を、モノドネで社会に役立つお品に変えませんか?