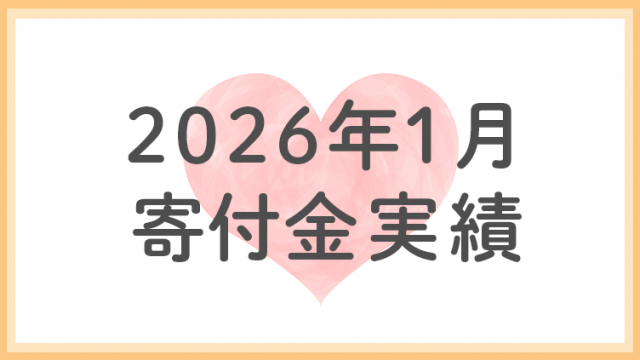ボランティア活動を行う際、特に気を付けるべきこと

本年1月1日に発生した能登半島地震では200名を超える死者を出し、現在も本当に多くの被災者が避難生活を送っています。
連日テレビなどで報道される被災地の状況を見て、心を痛めている人や何かしらの支援がしたいと感じている人も、少なくないのではないでしょうか。
中にはボランティア活動をしに、現地に行きたいと考えている人も多いと思いますが、被災地に行く時期や活動内容によっては、例え善意のボランティアであっても被災者の迷惑になってしまうことがあります。
今回はボランティア活動を行うにあたって、最低限気を付けるべきことや心構えについて説明します。
ボランティア活動を行うにあたって気を付けたいこと
ボランティア活動に取り組むにあたって気を付けたいことには、下記のようなものがあります。
- 相手の気持ちを尊重する
- 情報漏洩やプライバシーの侵害に繋がる行為はしない
- 積極的なコミュニケーションを心がける
- 活動のルールを守る
- 気付いたことは活動先の団体に報告する
一つずつ説明します。
相手の気持ちを尊重する
被災し避難生活を送っている人の中には、災害により大切なご家族やご友人を失くしてしまった人もいます。
人的な被害は無かったとしても、自宅や仕事を失くしてしまったという人もいるでしょう。
さらに慣れない避難生活で、大きなストレスや不安を抱えています。
自分にとっては何気ないつもりで行ったコミュニケーションが、被災者を深く傷つけてしまうことがあるかもしれません。
そうならないよう被災者の気持ちを尊重し、できる限り相手に寄り添った対応を心がけましょう。
自己満足で行うボランティアは、スラックティビズムと呼ばれます。
スラックティビズムとは、slacker(怠け者)とactivism(社会運動)を掛け合わせた造語で、社会に良いことをしようとしているようで、実際には良い影響を与えない行動のことを言います。
自分の行動がスラックティビズムになってないか、客観的に振り返ってみることも大切です。
情報漏洩やプライバシーの侵害に繋がる行為はしない
ボランティア中に知り得た情報は、絶対に第三者に漏らしてはいけません。
知り得た情報の中には、一般公開されていない内容が含まれている可能性があります。安易にインターネットやSNSへ、書き込むのは控えましょう。
また、許可を取らず写真を撮ることもNGです。
積極的なコミュニケーションを心がける
ボランティア活動を行う際は、積極的なコミュニケーションを心がけましょう。
人は分からない、知らないという不完全な状態にあることで、不安が醸成されてしまうことがあります。
被災者の中には多くの知らない人たちが出入りする状態に、不安を感じる人がいるかもしれません。
過度なコミュニケーションをする必要はありませんが、明るくハッキリとした挨拶や返事を心がけましょう。
またボランティア活動には、大変さや厳しさを感じることがあります。対被災者だけでなく、自分と同じようにボランティア活動に取り組む人たちとも積極的にコミュニケーションを図ることで、周囲の力を借りやすくなります。
ボランティアは、自発性が求められる活動です。受け身にならず、周囲の人たちと積極的なコミュニケーションを図るようにしましょう。
活動のルールを守る
活動先で取り決めたルールは、必ず守ります。
約束事やルールの背景には、必ず理由があります。自分勝手な判断で破ってはいけません。
ボランティア活動は、自分の自由な意思に基づいて行う活動ですが、自分勝手な判断でルールを破ったり約束を守らなかったりする人は信用されません。
ボランティア活動に参加する際は約束を守る、相手を尊重するなど社会人としてのマナーを守りましょう。
気付いたことは活動先の団体に報告する
ボランティア活動を行う中で、問題に直面することもあります。
ちょっとした違和感であっても、早めに対応することで大事に至らずに済むこともあるでしょう。また改善点であれば、今後、同じ活動を行う人たちの役に立つこともあります。
問題に直面したり疑問に感じたりすることがあれば、必ず一人で抱え込まず活動先の団体に報告や相談するようにしましょう。
災害ボランティアの3原則
被災地で開設される災害ボランティアセンターでは、ボランティア活動を希望する個人・団体の受け入れ調整やマッチング活動を行っています。
災害ボランティアセンターは、被災地の市区町村にある社会福祉協議会に開設されるケースが一般的です。
今回の能登半島地震でも被災した珠洲市や輪島市など、各市町村に災害ボランティアセンターが開設され、すでにそれぞれが情報発信などの活動を行っています。
災害ボランティアセンターが設置・活動を行うにあたって3原則としている考え方があります。
それは「被災者中心」「地元主体」「協働」です。
災害ボランティア活動の目的は被災者に寄り添い、日々の生活支援と生活再建に向けた取り組みのサポートを行うことです。
まれに「被災者の力になりたい」「支援したい」という思いが強すぎるのか、被災者が望む以上の、もしくは全く望んでいないような支援をしてしまうボランティアがいます。
前述したように、自己満足なボランティア活動はスラックティビズムと呼ばれ、社会に良いことをしているつもりでも、実際には良い影響を与えていません。
ボランティアを行う際は、必ず被災者の気持ちやプライバシーに配慮し、マナーある行動と言動を意識しましょう。
また活動に際して、現地の災害ボランティアセンターやボランティアコーディネーターなど地元受け入れ機関の指示や指導に必ず従います。
指示された内容が自分の経験や意向と異なることがあるかもしれませんが、被災地域ごとの状況や特性にも違いがあります。
地元機関からの指示には地域ならではの、さまざまな事情が加味されていることを忘れないようにしましょう。
上述した3原則以外に災害ボランティアセンターが発信している内容には、「被災地で活動する際の宿泊はボランティア自身が事前に手配する」というものもあります。
もちろん宿泊場所だけでなく、水、食料、その他必要なものについてもボランティア活動への参加者自身が用意し、準備を整えた上で活動に参加しなくてはなりません。
現地での、物資調達を前提とした参加は止めましょう。
まとめ
今回はボランティア活動を行うにあたって、最低限気を付けるべきことや心構えについて紹介しました。
ボランティア活動に参加する際は、自分自身で現地の情報をしっかりと収集し、参加するのかしないのか正しく判断する必要があります。
被災地での活動は危険が伴うことや、重労働となることもあります。また物資の調達や宿泊場所の手配など、ままならないことも多いでしょう。
準備が整わないと感じることがあれば、参加を見送る判断も大切です。
なお、災害ボランティアを希望される場合は必ず、事前に特設サイト等で受け入れ状況を確認するようにしましょう。また、2024年2月5日現在、事前登録後、決定通知を受けた方のみの活動となります。
参考:令和6年(2024年)能登半島地震に係る石川県災害ボランティア情報
災害ボランティア活動の3原則は「被災者中心」「地元主体」「協働」です。
災害ボランティアに参加する際は、良かれと思った自分の行動が被災者や他のボランティア参加者の負担や迷惑にならないよう、3原則を正しく守り活動に取組みましょう。
モノドネでは、あなたの不用品を寄付金に変えることができる新しい仕組みです。
もう使わないけど捨てるにはもったいない。
そういったお品を寄付金に変えませんか?
手続きは3ステップ
-
寄付したい団体を選ぶ
モノドネ掲載団体の中から、あなたが応援したい活動団体を選びます。
-
申し込みをする
申し込みフォームに必要事項を入力し、完了メールを受け取る。
-
寄付品を発送する。
メールに記載された発送先へお品を発送する。
※買取王国系列店舗への持ち込みも可能です(一部対象外店舗あり)。
発送されたお品を専任スタッフが査定し、その査定額全額があなたの選んだ活動団体への寄付金になります。
査定額はメールにてお知らせします。
選んだ活動団体が寄付金控除対象団体であれば、寄付金控除を受けられます。

お品はそれを必要とする次の誰かにお繋ぎし、リユース・リサイクルされます
あなたにとっての不用品を、モノドネで社会に役立つお品に変えませんか?