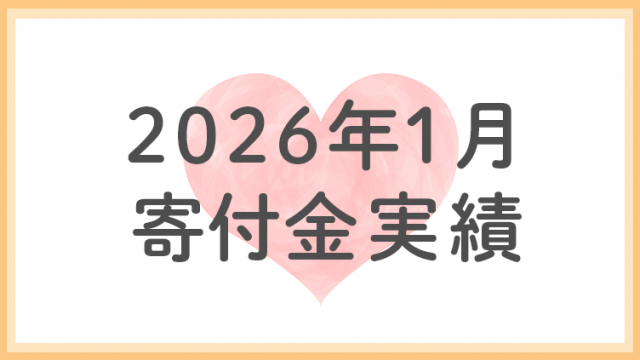活動の安心感につながる!ボランティア保険について

ボランティアにはさまざまな種類がありますが、特に被災地で行うボランティア活動では、危険を伴うことや重労働になることも少なくありません。
また、意図せず他人のモノを壊してしまったりケガを負わせてしまったりするリスクもあります。
今回は加入することで、活動の安心感にもつながるボランティア保険について紹介します。
ボランティア保険とは
ボランティア保険とは、ボランティア活動中のケガや損害賠償を補償してくれる保険です。
社会福祉協議会が窓口になっており、加入にあたっては社会福祉協議会に登録する必要があります。
ボランティア保険の保険期間は、4月1日から翌年3月31日までの一年間です。
一度加入すると保険期間内の、かつ条件を満たす活動に限り、他のグループにおけるボランティア活動についても補償の対象となります。
年度の途中での加入となった場合は、加入手続き完了日の翌日0時より該当年度の3月31日までが保険期間です。
ボランティア保険の補償内容
ボランティア保険で補償される範囲は、以下の2つです。
- 加入者本人の死亡、ケガ
- 相手の死亡、ケガ、財産への賠償責任
「加入者本人の死亡、ケア」の補償内容については、下記のように分類されます。
- 死亡・後遺症
- 入院、手術、通院
- 特定感染症
一つずつ説明します。
死亡・後遺症
加入者本人がボランティア活動中の急激、かつ偶然な外来の事故により死亡もしくは後遺症が残った場合に補償されます。
急激とは突発的に発生することをさし、偶然とは予知されない出来事をいいます。外来とは原因が加入者本人ではなく、加入者本人の体の外からの作用によることを表します。
上記にはボランティア活動中だけでなく、活動に向かう途中の交通事故なども補償の対象に含まれます。
入院、手術、通院
ボランティア活動中に、「重いものを持ちあげ腰を痛めたため、通院した」「転んで骨折し、手術が必要になった」場合も補償の対象です。
また「熱中症になり入院した」「食べた弁当が原因で、食中毒になり通院した」など、ケガ以外の入院や通院も補償に含まれます。
特定感染症
ボランティア保険は活動中の事故やケガだけでなく、特定感染症にかかった際も補償されます。
特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定される一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型コロナウィルス感染症をさします。
新型コロナウィルスについては重症化リスクが高い人のみが補償の対象になっています(2022年12月時点)。
参考:社会福祉法人 全国社会福祉協議会|ボランティア活動保険加入>ボランティア活動保険パンフレット(令和5年度版)より
特に特定感染症については今後、規約が変更される可能性がありますので、ボランティア保険へ加入する前に確認するようにしましょう。
もう一つの補償対象である「相手の死亡、ケガ、財産への賠償責任」について説明します。
「相手の死亡、ケガ、財産への賠償責任」では、「家事援助中に手が滑り、食器を割ってしまった」「誤って車イスを転倒させてしまい、お年寄りにケガさせてしまった」などが、補償の対象です。
こちらについてもボランティア活動中だけでなく、活動に向かう途中の交通事故なども補償の対象になります。
起こってしまったアクシデントが補償の対象になるか否か、判断に迷う時は必ず確認するようにしましょう。
ボランティア保険への加入方法
ボランティア保険への加入手続きは、社会福祉協議会で行います。
社会福祉協議会とは、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした、非営利組織です。
最寄りの社会福祉協議会に行き必要事項を記入した申請用紙を提出後、銀行もしくは郵便局で保険料を振り込めば、ボランティア保険への加入手続きは完了です。
社会福祉協議会には、「市区町村社会福祉協議会」「都道府県社会福祉協議会」「全国社会福祉協議会」の3種類があります。
ボランティア保険の加入に際しては、最寄りの「市区町村社会福祉協議会」に行きましょう。
市区町村社会福祉協議会は、地域の最前線で福祉を支えている組織であり、地域のボランティア活動に関する相談や活動先の紹介なども行っています。
なお、原則、ボランティア保険の加入手続きをインターネットで行うことはできません。
災害時のみ特例として、インターネットで加入手続きができますが、その際の保険料の支払いはクレジットカードのみが対象となります。
クレジットカードを持っていない、もしくはクレジットカードでの支払いを希望しない場合は、事前にお近くの市区町村社会福祉協議会でボランティア保険への加入手続きを済ませておくことをお薦めします。
補償対象のボランティア活動について
ボランティア保険の補償対象になるのは、日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」かつ、下記に該当するいずれかの活動のみです。
- 社会福祉協議会に登録されたグループの会則に則り企画、立案された活動
- 社会福祉協議会に届け出している活動
- 社会福祉協議会に委嘱された活動
- 特定非営利活動促進法(NPO法)に規定する特定非営利活動
ボランティア活動中だけでなく、自宅などと活動を実施する場所を往復する際に発生した事故やアクシデントも、ボランティア保険の補償対象に含まれます。
またボランティア活動の実施を前提とした学習会や会議なども、補償の対象です。
補償対象外のボランティア活動とは
自発的意思とは考えにくい活動は、ボランティア保険の補償対象には含まれません。
自発的な意思とは考えにくい活動とは具体的には、「学校などの管理下で行う先生・生徒の活動」「道路交通法違反者による、行政処分としての活動」「免許や資格の取得を目的とした活動」などです。
上述した活動の他に、ボランティア保険の補償対象外となる活動には
- PTAや自治体、老人クラブ、子ども会などボランティア活動以外の目的で作られた団体やグループの事業
- 有償での活動
- 自宅で行うもの
- 企業など営利事業の一環として行うもの
- 山岳・海難救助や害獣駆除など、規約上対象外となっている活動
などがあります。
スポーツ競技などでは競技者としての参加はボランティア保険の補償対象にはならないものの、教えたり福祉を目的としていたりする場合に限り補償対象になるものもあります。
詳しくは、最寄りの社会福祉協議会に問い合わせをすることをお薦めします。
ボランティア保険の補償対象外となるボランティア活動に参加するにあたって、個人で損害保険に加入している人も多くいます。
損害保険に個人賠償責任保険をセットすれば、ボランティア保険に近い補償が得られます。
必要に応じて損害保険代理店や、保険会社が運営するWebサイトでチェックしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、ボランティア活動に参加する前に加入しておきたいボランティア保険について紹介しました。
ボランティア保険は、安価な金額から加入でき年度内の活動が補償されます。
加入することで本人だけでなく、周りの人も安心して作業できるようになります。ボランティア活動に参加する際は、ボランティア保険への加入を強くお薦めします。
モノドネでは、あなたの不用品を寄付金に変えることができる新しい仕組みです。
もう使わないけど捨てるにはもったいない。
そういったお品を寄付金に変えませんか?
手続きは3ステップ
-
寄付したい団体を選ぶ
モノドネ掲載団体の中から、あなたが応援したい活動団体を選びます。
-
申し込みをする
申し込みフォームに必要事項を入力し、完了メールを受け取る。
-
寄付品を発送する。
メールに記載された発送先へお品を発送する。
※買取王国系列店舗への持ち込みも可能です(一部対象外店舗あり)。
発送されたお品を専任スタッフが査定し、その査定額全額があなたの選んだ活動団体への寄付金になります。
査定額はメールにてお知らせします。
選んだ活動団体が寄付金控除対象団体であれば、寄付金控除を受けられます。

お品はそれを必要とする次の誰かにお繋ぎし、リユース・リサイクルされます
あなたにとっての不用品を、モノドネで社会に役立つお品に変えませんか?