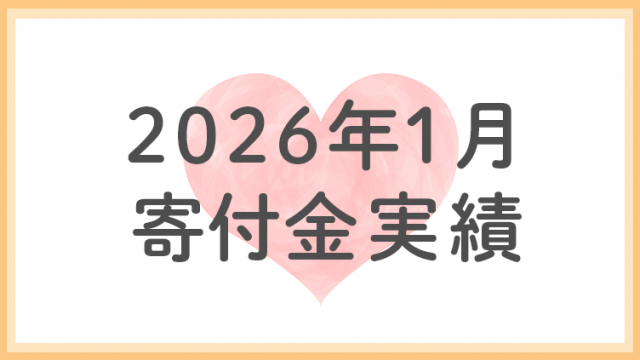個人で送る救援物資|被災地支援の前に気をつけたいこと

昨今、個人からの救援物資について「送るのは控えてほしい」「受け付けていない」という対応をとる被災地が増えています。
その理由は、個人からの救援物資は扱いが難しいということにあるようです。
本記事では、「個人が被災地に救援物資を送る前に知っておきたいこと」について紹介します。
個人での物資支援は難しい
1月1日に発生した能登半島地震で大きな被害に見舞われた石川県では、2月23日現在、仕分けなどの手間を理由に個人からの救援物資の受け付けは行っていません。
令和6年(2024年)能登半島地震に係る義援物資の受入について | 石川県 (ishikawa.lg.jp)
「個人から送られてくる救援物資は扱うのが難しい」といわれている理由の一つに、仕分けの手間があります。
個人からの救援物資は同じ段ボールの中に食品や衣類、学習用品などが混在していることが多く、それらを開封し仕分ける必要があります。
避難所は被災した被災者が中心となり運営管理しているため、各個人から送られてきた大量の救援物資を一つひとつ開封し、仕分け、管理まで行うノウハウはほとんどありません。
また送られてきた救援物資の中には、大量の食品や生鮮野菜、冷蔵が必要な加工品などが入っているケースもあります。
中には配送される途中で食材が腐ってしまい、一緒に入っていた毛布や学習用品も廃棄せざるを得ない場合もあるそうです。
救援物資が「第二の災害」と呼ばれることも
「水が足りない」「食品が欲しい」など、テレビやSNSで被災者が発信するメッセージを受け取り、それらを救援物資として送る人もいます。
しかしながら日本国内の場合、災害で直ちにモノがなくなることはほぼなく、災害により交通やライフラインが断たれてしまい一時的に品不足になっているだけです。
交通やライフラインが回復し個人からの水や食品が届くころには、すでに自治体や企業から大量の救援物資が届いています。
また被災地で必要とされる物資は、状況により都度かわります。
受け取り手がいなくなった物資は不良在庫となり、最後の最後まで余ってしまった救援物資は廃棄されます。
もちろん、廃棄にかかる処分代は無料ではありません。
実は、良かれと思って送られてきた救援物資が、被災地で困難を招き「第二の災害」と呼ばれてしまうケースは少なくありません。
このような問題が認識されたきっかけは、1993年の北海道西南沖地震だといわれます。
この時も日本各地から多くの救援物資が届けられましたが、うち1,200万トン近い衣類が廃棄処分になったといわれます。
また1995年に発生した阪神・淡路大震災では、約100万個の小包が救援物資として届けられ、廃棄処分するのに2,300万円もの大金がかかったという報道もあります。
救援物資が第二の災害といわれてしまう理由は、廃棄の問題だけではありません。
本来であれば善意のはずの救援物資の中に、受け取る側である被災者にとって迷惑でしかないモノが含まれていることがあります。
このようなモノは置く場所や保管に困るだけでなく、それでなくても負担の大きい被災者を疲弊させてしまいます。
救援物資を送る前に気を付けたいこと
救援物資は言うまでもなく、被災地の生活や復興を支援するためのモノです。
救援物資として何が必要かは受け取る側が決めるべきであり、送る側の勝手な判断で物資を送ってはいけません。
自宅などで使用する機会がなく放置されていたモノや、余っているモノを救援物資として送ることも控えましょう。
もし自宅にあるモノを活用して被災地への支援を行いたいのであれば、それらのモノをフリーマーケットやフリマアプリで換金し、義援金として被災地に送るのはいかがでしょうか。
思うような金額にはならないかもしれませんが、救援物資を送るのに必要となる段ボール箱の送料も安くはありません。
送料を上乗せして被災地に送れば、ある程度のまとまった金額になります。
それでもやはり物資が送りたいという方は送る前に本当に被災地のためになるのか、よく考えてから送るようにしましょう。
以下のようなモノについては特に注意が必要です。
- 古着
- 食品
- 薬やサプリメント
- 家電
- 千羽鶴や寄せ書き、など
一つずつ説明します。
古着
救援物資として古着を送る際には、「季節にあっているか」「自分がもらったら嬉しいか」を基準に考えましょう。
世界有数の豪雪地帯ともいわれる北陸地方で、この時期に半袖やランニングを喜んで着る人はいません。
また、洗濯してあるかどうかさえも分からなかったりする服は被災者の役に立たないでしょう。
たとえ救援物資であったとしても、自分が要らないモノを人に送ってはいけません。
食品
調理を前提とした生鮮食品を送るのも、止めましょう。
調理できる場所があるかどうかも分かりませんし、配送の途中で腐ってしまうこともあります。
保存できるからと冷凍食品を救援物資として送る人がいますが、配送の途中で解凍されてしまったり被災地に着いても冷凍庫が使えなかったりする可能性もあります。
また成分表のない食品はアレルギー成分の確認が難しく、廃棄処分となる可能性が高いです。
薬やサプリメント
過去に救援物資として、薬局で処方されたと思われる薬が送られてきた自治体があるそうです。
他人が処方された薬を使うわけにはいきませんし、効用が分からないサプリメントを口にする人はいません。
家電
電子レンジや一部の洗濯機、蛍光灯器具は周波数が異なると使用できない場合があります。
仮に使用できたとしても性能が低下したり、火災の原因になったりすることもあります。
そもそも家電は大きくかさばります。そのため安易に送るのは、お薦めしません。
千羽鶴や寄せ書き
避難所には多くの被災者が押し寄せ、個々の荷物を置く場所すらままならないほどスペースに余裕がない場合が多いです。
また避難所では、最新の情報や連絡事項が壁に貼りだされることも多く、千羽鶴や寄せ書きを飾るスペースはありません。
災害直後の被災地は混乱しています。被災地の生活や復興支援に直結しないモノを送ることは、控えましょう。
物資を送る場合は団体などを通じて送る
被災地支援をしているNPO法人やボランティア団体などが、物資の募集をしていることがあります。
これらの団体は被災自治体と直接連絡を取り合い要望に添ったモノを募集したり、過去の経験から本当に必要とされるモノに限定し募集したりしていることがほとんどです。
お金ではなくモノで支援したいという方は、被災地に直接ではなくNPO法人やボランティア団体を経由し、救援物資を送るのも一つのアイデアです。
もちろん募集しているからといって、いきなり送り付けるのではなく、事前に団体のホームページを確認し募集している具体的な物資や、募集期間などを確認するようにしましょう。
まとめ
今回は、個人が救援物資を送る前に気をつけたいことについて紹介しました。
個人からの物資は受け付けていないという自治体も増えていますが、「時期や物資を限定し、受け付けている」「受け付けていたが、募集は終了した」など、その対応はさまざまです。
実際に、今回の能登半島地震で石川県と同じように被災した富山県では、すでに救援物資の受け付けを終了させていますし、新潟県では始めから物資の募集は行っていません。
このように自治体によっても対応は異なりますので、こちらについても必ずホームページで最新の情報をチェックするようにしましょう。
モノドネでは、あなたの不用品を寄付金に変えることができる新しい仕組みです。
もう使わないけど捨てるにはもったいない。
そういったお品を寄付金に変えませんか?
手続きは3ステップ
-
寄付したい団体を選ぶ
モノドネ掲載団体の中から、あなたが応援したい活動団体を選びます。
-
申し込みをする
申し込みフォームに必要事項を入力し、完了メールを受け取る。
-
寄付品を発送する。
メールに記載された発送先へお品を発送する。
※買取王国系列店舗への持ち込みも可能です(一部対象外店舗あり)。
発送されたお品を専任スタッフが査定し、その査定額全額があなたの選んだ活動団体への寄付金になります。
査定額はメールにてお知らせします。
選んだ活動団体が寄付金控除対象団体であれば、寄付金控除を受けられます。

お品はそれを必要とする次の誰かにお繋ぎし、リユース・リサイクルされます
あなたにとっての不用品を、モノドネで社会に役立つお品に変えませんか?