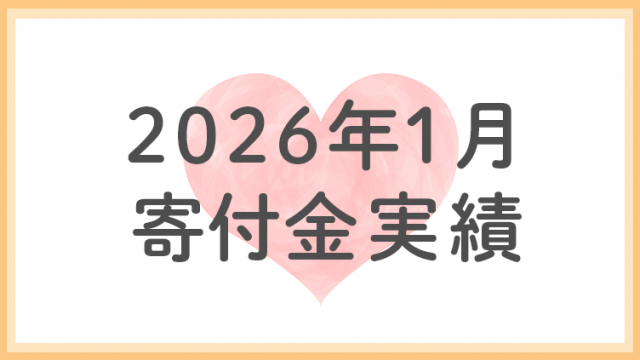生前整理での寄付の方法を紹介!|寄付を行うメリットや税制優遇について解説!

生きていく中で、いつの間にか増えていく持ち物。「もう使わないけれど、まだ使えるから捨てるのはもったいない」と感じている方も多いのではないでしょうか。 そんなとき、一つの選択肢として考えられるのが「寄付」です。
生前整理の一環として物品を寄付することで、社会貢献としても、税制面でも、さまざまなメリットが得られます。 この記事では、生前整理における寄付の可能性から具体的な方法まで、詳しく解説していきます。寄付を通じて、大切にしてきた物に新たな価値を見出してみたいと感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
生前整理で寄付をすることは可能?

生前整理で寄付をすることは可能です。使わなくなった本を寄付したり、着なくなった服を福祉施設に届けたりすることで、物を必要としている方々の役に立てます。
例えば、子どもが使っていた学習机を寄付すれば、勉強に励む子どもたちの力になれるでしょう。
ただし、生前整理で寄付をするときには、寄付先の規定をしっかり確認することが大切です。
生前整理で寄付をするメリット

それでは次に、生前整理で寄付を行うメリットを見ていきましょう。
- 税制上の優遇措置を受けることができる
- 家族の負担を減らすことができる
- 必要な人へ確実に届けることができる
- 社会貢献への達成感を得られる
それぞれ詳しく見ていきます。
税制上の優遇措置を受けることができる
生前整理での寄付によって、税制上のメリットを受けられます。
例えば、家具や書籍、衣類などを認定NPO法人に寄付すると、その評価額に応じて税制優遇を受けられます。具体的には、寄付金額から2,000円を引いた額が所得税から控除されます。年収400万円の方が3万円相当の評価額の物品を寄付した場合、28,000円が所得控除されます。
一方、遺品として残した場合、相続時に相続税の対象となり、相続人に大きな税負担が生じることもあります。 生前に寄付をすることで、税制優遇を受けながら社会貢献もできるのです。さらに、寄付先から発行される受領証明書があれば、確定申告の手続きもスムーズです。
家族の負担を減らすことができる
ご遺族の方が遺品整理を行う場合、大切な思い出の品と不要なものの区別に悩み、心労が重なることがよくあります。しかし、生前に自分で整理して寄付しておけば、ご遺族がその判断に迷う心配はありません。 例えば、趣味で集めた切手コレクションを寄付したり、読み終えた専門書を図書館に寄贈したりすることで、ご遺族の物理的な整理の手間も大幅に減ります。
また、寄付を通じて自分の想いや価値観を家族と共有できる機会にもなります。このように、生前整理は家族への最後の贈り物になるといえるでしょう。
必要な人へ確実に届けることができる
生前整理での寄付は、大切にしてきた物を本当に必要としている人へ直接届けることができます。
使わなくなった車椅子を寄付すれば、すぐに必要な方の移動手段として活用されます。また、子育て用品を寄付すれば、経済的に支援が必要な家庭の子どもたちの成長を支えられるでしょう。
さらに、寄付先の団体から物品の活用状況を知らせてもらえることもあります。自分の大切にしていた物が誰かの役に立っているという実感は、何物にも代えがたい喜びとなります。
社会貢献への達成感を得られる
生前整理での寄付によって、思いがけない喜びを得られる場合があります。例えば、これまでに使用していた食器などを寄付することで、さまざまな施設で使ってくれる可能性があります。
物を整理して手放すことは終わりではなく、むしろ地域社会での新しい役割を見つける始まりとなることがあります。
生前整理で寄付する際の注意点

様々なメリットがある一方、生前整理で寄付を行う際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。
ここでは、生前整理で寄付する際の注意点を3つ紹介します。
- 家族の同意を得ることが重要
- 寄付先の信頼性を確認する必要がある
- 寄付金受領証を保管しておかなければならない
それぞれ詳しく解説します。
家族の同意を得ることが重要
生前整理での寄付には、必ず家族の同意を得ることが大切です。特に相続対象となりうる高額な物品や、家族との思い出が詰まった品物を寄付する際は慎重な確認が必要です。
まずは、寄付を考えている物品のリストを作成し、家族会議を開いて一つずつ確認していくことをおすすめします。 家族の同意をとるために確認したいことは以下の3つです。
- 金銭的価値の確認
- 思い出の品としての価値の確認
- 寄付先の選定についての合意確認
これらを事前に話し合うことで、寄付後のトラブルを防ぐことができます。特に遺産分割の対象となる可能性のある物品については、書面で家族の同意を残しておくと安心です。
寄付先の信頼性を確認する必要がある
大切な物が正しく使われるように、寄付先の信頼性を確認することが大切です。
確認すべきポイントは次の3つです。
- 団体の法人格(認定NPO法人や公益財団法人など)
- 活動実績や財務状況
- 寄付後のフローの確認
特に気を付けたいのは、寄付品の使用目的が明確に示されているかどうかです。信頼できる団体は、寄付品の活用方法や受け入れ条件を具体的に説明してくれます。
不安な場合は、実際に団体を訪問したり、過去の寄付者の声を聞いたりすることで、より確実な判断ができます。
このように慎重に確認することで、寄付先に安心して物品を届けられるでしょう。
寄付金受領証を保管しておかなければならない
確定申告で税制優遇を受ける場合、寄付金控除の証明として寄付先が発行した寄付金受領書(領収書)を確定申告が完了するまでは保管する必要があります。
寄付金受領書があれば、必ず税制優遇を受けられるわけではありません。
税制優遇の対象となる寄付先は決められていますので、寄付の前に対象かどうか確認が必要です。
生前整理で寄付を行う方法

ここまで生前整理で寄付を行う方法について紹介してきました。しかし、いざ寄附をしようとしたとき「どうやって寄付をすればいいの?」と迷いますよね。
ここでは、生前整理で寄付を行う手順を紹介します。
- 寄付できるものを仕分けする
- 適切な寄付先を選択する
- 寄付の手続きを行う
- 税制上の手続きを確認する
それぞれの手順を詳しく解説します。
寄付できるものを仕分けする
寄付品の仕分けは、基準に従って行うことで、効率的に整理できます。以下の表を参考に分類していきましょう。
| 分類基準 | 確認ポイント | 具体例 |
|---|---|---|
| 状態チェック | ・汚れ/破損の有無 ・動作確認 ・部品の過不足 | ・シミや破れのない衣類 ・正常に動く電化製品 ・セット品が揃った食器 |
| 種類を振り分ける | ・季節性 ・用途 ・対象年齢 | ・冬物コート(季節) ・学習参考書(用途) ・子供服(対象年齢) |
| 寄付先の基準を見極める | ・受入基準 ・需要の有無 ・搬送方法 | ・福祉施設向け介護用品 ・図書館向け書籍 ・児童施設向け玩具 |
仕分けを始める前に、まず寄付先の受け入れ基準を確認することが大切です。また、「自分が必要とする側だったら使いたいか?」という視点で判断すると、より適切な仕分けができます。迷った際は、寄付先に事前に問い合わせることをおすすめします。
適切な寄付先を選択する
上述しましたが、3つの基準で適切な寄付先を選択しましょう。
- 団体の法人格(認定NPO法人や公益財団法人など)
- 活動実績や財務状況
- 寄付後のフローの確認
この基準を守りつつ寄付先を選定することで、ご自身の大切にしたものが適切な団体に寄付され、有効活用されるでしょう。
寄付の手続きを行う
寄付の手続きは、基本的に4つのステップで進めていきます。まず初めに、寄付先への事前連絡を行います。この際、寄付したい物品のリストや状態を伝え、受け入れ可能かどうかの確認を取ります。多くの団体では、メールや電話での問い合わせから手続きが始まります。
次に、必要書類の準備と提出を行います。寄付申込書の記入や、物品の写真提供、身分証明書のコピーなどが求められることがあります。その後、実際の寄付品の引き渡しとなります。団体による引き取りサービスを利用するか、自身で持ち込むかを選択します。 最後に、寄付金控除を受ける場合は、受領証明書の発行を依頼します。
この証明書は確定申告の際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。各手続きの詳細は団体によって異なるので、事前にしっかりと確認することが重要です。
税制上の手続きを確認する
寄付に関する税制上の手続きは、確定申告を通じて行います。特に物品寄付の場合は、適切な評価額の算定が重要になるため、以下のステップに従って慎重に進めていきましょう。
- 寄付先の確認 ・認定NPO法人や公益社団法人かどうかの確認 ・税制優遇対象団体であることの確認
- 確定申告の実施 ・寄付金控除の申告書への記入 ・証明書類の添付 ・期限内の申告(2月16日~3月15日)
寄付金控除を確実に受けるためには、これらの手続きを正確に行うことが重要です。特に物品寄付の評価額については、必要に応じて税理士に相談することをおすすめします。
手続きに不安がある場合は、早めに税務署や専門家に相談することで、適切な税制優遇を受けることができます。
生前整理を素早く行うならモノドネがおすすめ!
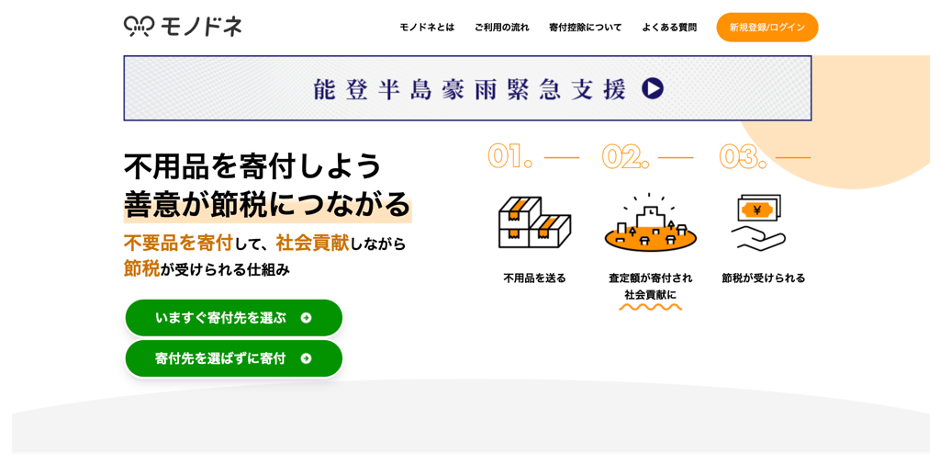
モノドネは、生前整理をスマートに進められる画期的なサービスです。不要になったモノをお金に換えて寄付できる仕組みにより、幅広い支援が可能になります。
例えば、古い家具や書籍をモノドネに出すと、その査定額が希望の支援団体に寄付金として届けられます。モノドネの特徴は以下の通りです。
- モノが必要な人へ適正価格で販売される
- 査定額が寄付金として支援団体へ届けられる
- 生前整理と社会貢献が同時に実現可能
生前整理をする方、モノを必要とする方、支援を必要とする団体の三者がみな恩恵を受けられるため、非常に魅力的なサービスとなっています。詳しい情報が知りたい方は、以下の公式サイトをご確認ください。
参照:モノドネHP
まとめ
生前整理での寄付は、個人と社会をつなぐ素晴らしい取り組みといえます。税制優遇を受けられるだけでなく、遺族の負担軽減にもつながり、さらには必要としている方々への支援も実現できます。
ただし、寄付を行う際は、いくつかの重要なポイントに注意が必要です。家族の同意を得ること、寄付先の信頼性を確認すること、そして税制優遇を希望するときは寄付先が対象の団体かどうか、寄付金受領書の保管などです。 寄付の手順としては、まず物品の仕分けを行い、適切な寄付先を選択し、必要な手続きを進めていきます。特に税制上の手続きは慎重に行う必要があります。
また、モノドネのようなサービスを活用すれば、より手軽に寄付を実現することも可能です。 大切なものを誰かの役に立てる喜び、そして社会貢献への達成感。生前整理での寄付は、モノを手放す以上の価値を私たちに与えてくれるはずです。ぜひ本記事の内容も参考に、生前整理の寄付を始めてみてください。
モノドネでは、あなたの不用品を寄付金に変えることができる新しい仕組みです。
もう使わないけど捨てるにはもったいない。
そういったお品を寄付金に変えませんか?
手続きは3ステップ
-
寄付したい団体を選ぶ
モノドネ掲載団体の中から、あなたが応援したい活動団体を選びます。
-
申し込みをする
申し込みフォームに必要事項を入力し、完了メールを受け取る。
-
寄付品を発送する。
メールに記載された発送先へお品を発送する。
※買取王国系列店舗への持ち込みも可能です(一部対象外店舗あり)。
発送されたお品を専任スタッフが査定し、その査定額全額があなたの選んだ活動団体への寄付金になります。
査定額はメールにてお知らせします。
選んだ活動団体が寄付金控除対象団体であれば、寄付金控除を受けられます。

お品はそれを必要とする次の誰かにお繋ぎし、リユース・リサイクルされます
あなたにとっての不用品を、モノドネで社会に役立つお品に変えませんか?