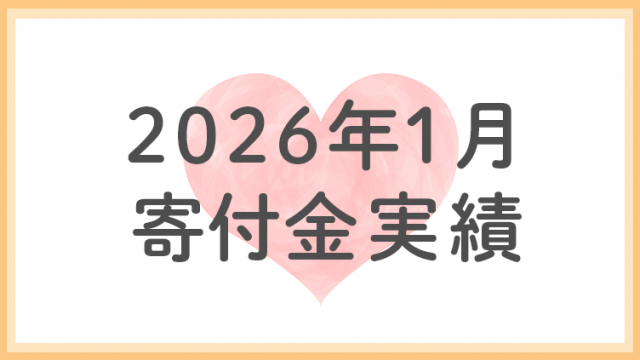寄付をするなら、どこに?何を?寄付先の選び方

「寄付で社会貢献してみよう」
そう思って行動したとき、最初に立ちはだかる壁が寄付先の選び方です。寄付するには、かならず対象となる相手が必要です。
世の中にはNPOや自治体など数多く寄付できる場所があるなかで、一体どこに寄付したらいいのか迷う方も多いのではないでしょうか。
ユニセフや赤い羽根共同募金などは昔から馴染み深いですが、最近では「クラウドファンディング」や「インターネット募金」など、寄付の多様化が進んでいます。
「世間の人たちは何を基準に寄付先を選んでいるの?」
「自分に合った寄付先を見つけるには?」
「寄付するときに見るべきポイントは?」など
今回のモノドネでは寄付先の選び方をわかりやすくガイドしたいと思います。
目次
- 寄付先はどうやって選ぶべき?
- 寄付先を目的から選ぶ
・活動内容から選ぶ
・寄付できる(したい)モノから選ぶ
・お世話になった(なっている)場所から選ぶ
・寄付団体から選ぶ
- 団体選びでは信用性・信頼性も大切
- まとめ
1.寄付先はどうやって選ぶべき?
寄付先を選ぶ前に、まずは「なぜ寄付するのか」目的を整理することが大切です。寄付は英語で”donation”、その意味は「寄付するものが自らの意志で、金銭または財産を無償で提供すること」です。つまり寄付には金銭的リターンがありません。
もし皆さんが今「寄付したい」と思っている場合、なんらかの目的があるはずです。「地球上で困っている子どもを助けたい」など、漠然としていても構いません。「昔、ある方(または学校や施設)にお世話になった」「寄附金控除を受けたい」と具体的な理由をお持ちの方もいるでしょう。
寄付の目的やきっかけは寄付する人によって違いますし、支援できるのは何も「団体だけではない」「金銭だけではない」ことを理解していただきたいのです。寄付先の選び方と一口にいっても、その方法は多種多様です。
もちろん多くのメディア(インターネットや新聞記事)で紹介される団体に寄付することも正しいですが、せっかく社会貢献するなら”自分にとって意義や意味の感じること”に寄付するのも選択の一つと言えます。
寄付の目的は?何を寄付する?「目的」から選ぶのも◎
|
2.寄付先を目的から選ぶ
さまざま寄付先の選び方をざっと紹介しましたが、ここでは目的ごとに詳しく見ていきます。
活動内容から選ぶ
1つ目は活動内容から選ぶ方法です。当然ながら寄付する場所によって活動内容は違います。たとえばNPOを例にすると、以下のような取り組みがあります。
災害・復興支援
大規模な災害(地震・火災・台風など)が発生したときに、被災者や現地のひとの心のケアをしたり、安心した生活ができるよう物品の供給や復興支援をおこないます。一例として、2011年3月11日に起きた東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)発生時には多くのNPOが支援活動に参加し、被災地の復興や被災者のサポートをおこないました。
福祉(高齢者・障がい者)
現代の日本では、少子高齢化が進んでいます。数多い高齢者のなかには、老人ホームに入ることができず生活に苦しむ方もいます。こうした「生活困窮者」を対象にした施設を運営して、当たり前のことができる生活をサポートします。
高齢者と同じく、障がい者を支援する団体も数多くあります。障がいといっても「重複障がい」「認知障害」「知的障がい」など対象は多岐にわたり、障がい者の環境に合わせた生活支援や就労支援をおこないます。
また障がいを持つ・持たないに関わらず、人とのつながりを理念とする団体もあります。
動物
日本では毎年、多くの犬や猫の殺処分がおこなわれているのをご存じでしょうか。環境省が発表したデータによれば、2020年に殺処分された犬猫は「約23,000匹」。この現実は同じ命あるものとして重く受け止めるべき問題といえます。
里親募集やコミュニティの場づくりなど、こうした殺処分の撲滅を促進する団体も増えてきています。動物に深い思い入れがあるという方は、ぜひ動物保護に取り組むNPOを応援してあげるのもひとつです。
貧困
貧困と聞くと「海外の問題では?」と考える方もいますが、じつは日本でも貧困は問題視されています。とくに子どもの貧困は深刻化しています。2019年、厚生労働省は7人に1人の子どもが「相対的貧困」と発表しました。
貧困には相対的貧困と絶対的貧困があります。相対的貧困とは「その国の水準よりも貧しい状態」、絶対的貧困とは「国や水準に関係なく、生きる上での生活がおこなえていない状態」です。
貧困は「子どもが学校に通えない」「十分な栄養がとれない」といった問題だけでなく、「家庭内暴力」「虐待」と負の連鎖を引き起こす原因にもなります。
貧困を対象にした団体では、学校にいけない子どもたちが学べる機会や、進学のための奨学金支援をおこなっています。また子どもの家族を支援することも多いです。
女性
子育てやDVなど、女性が抱える問題に特化した団体もあります。
国際協力NGOジョイセフ(JOICFP)
ジョイセフでは、性による健康の格差とジェンダー不平等に苦しむ女性たちが命と健康を守り、性と生殖における自己決定権を持つことができるよう支援活動を行っています。
今まで40を超える国や地域で支援活動を行ってきた、日本生まれの国際協力NGOです。
一般社団法人グラミン日本
グラミン日本は、主にシングルマザーを中心とした生活に困窮する方々へ、低利・無担保での少額融資や就労支援活動を行っている団体です。
チャンスを願い一歩を踏み出そうとしている人びとの伴走者として、誰もがいきいきと社会で活躍し、持続する社会づくりを目指しています。
特定非営利活動法人フローレンス
フローレンスは、みんなで子どもたちを抱きしめ子育てと共になんでも挑戦でき、いろんな家族の笑顔があふれる社会を目指し活動している認定NPO法人です。
主に一人親、待機児童問題、障害児保育・支援問題、貧困、虐待など子育てに関わるさまざまな問題に取り組んでいます。
食べ物
日本では毎年、多くの食べ物が役目を果たさずに捨てられています。農林水産省によれば、2020年の食品ロスは612万トン(東京ドーム5つ分)。国民一人ひとりが毎日「茶碗一杯分」の食べ物を捨てている計算です。
さらに世界人口の9人に1人は飢餓に苦しんでおり、5歳未満については年間310万人が栄養不足で命を落としています。この現状を少しでも減らすために、日本ではフードバンク活動(食品を集めて支援する)に取り組む団体もあります。またSDGs目標の2番目には「飢餓をゼロに」とも宣言されており、こうしたフードロス活動は寄付だけでなく普段の生活にも取り入れることができます。
フードバンクを行うある団体ではコロナ禍前に比べて2.5倍以上も需要が伸びています。
まちづくり
その場所に住む人たちが安心・安全に暮らすため、また自然環境を生かした観光業の盛り上げなど、地域の街づくりを中心とした活動もあります。お世話になった地域に恩返しがしたいと考える方は、まちづくりに貢献する団体を応援してみるとよいでしょう。
また地域の街づくりに関しては、地方自治体でも盛んにおこなわれています。
環境保護
人びとが普段から肉や魚、水などを安心して口にできるのは環境保全があってのこと。たとえばゴミを放置して地球温暖化が加速すれば、農作物などの収穫量の低下、牛乳や肉の生産量低下、水質の悪化にも影響します。
近年は、日本でもエコロジーや環境保全に関する取り組みは活発です。海や山などの自然が好きな方は、環境保全の取り組みに寄付してみると良いでしょう。
国際協力
海外の問題に興味がある場合は、国際協力をおこなう団体も視野にいれてみてください。一口に国際協力といっても、人材育成、緊急復興支援、ジェンダー平等、元子ども兵の支援など取り組みはさまざまです。
また国際協力を中心とする団体は、別名「NGO」と呼びます。
紹介した以外にも数多くの活動があります。まずは自分が興味あるジャンル探しから始めてみましょう。
寄付できる(したい)モノから選ぶ
2つ目が寄付するモノから選ぶ方法です。
「寄付はお金でしかできないの?」
このように寄付の対象が金銭だけと思っていた方も中にはいるかもしれません。実は金銭以外の寄付を受け付けている団体もあります。
金銭での寄付にハードルを感じていらっしゃる方は、すぐに始められる「物品での寄付」もおすすめです。どういったものが寄付できるのか、注意点も合わせて見ていきましょう。
書き損じはがき
書き損じはがきの寄付は数多くの団体でおこなえます。基本的には郵便はがきや年賀はがきが対象で、世界の子どもたちへワクチン提供や学習支援などに貢献できます。たとえば認定NPO法人テラ・ルネッサンスでは、集めた書き損じはがきを一度換金して、その収益をカンボジアやウガンダの人びとのために使います。
| 「テラ・ルネッサンスの活動資金」に変わるまで |
|---|
|
なおハガキを切手に交換する際の手数料は、寄付者が負担するケースが多いです。
切手(未使用または、使用済み切手)
切手を直接寄付することもできます。11万人以上の遺児学生を支援した実績をもつ「あしなが育英会(詳しくみる)」では、書き損じハガキはもちろん、未使用切手での寄付が可能です。また切手やハガキ以外にも、未使用のプリペイドカードや商品券(額面での寄付)にも対応しています。
昔収集したけど使わない記念切手などがあれば、ぜひ切手の寄付も検討してみましょう。中には使用済み切手を受け付けている団体もあります。
〈あしなが育英会の郵送先〉 〒102-8639 東京都千代田区平河町2丁目7−5 砂防会館4F 一般財団法人あしなが育英会 管理部寄付課 |
本
本も寄付できます。昔読んだ本が、当時のまま家に眠っているという方も多いのではないでしょうか。年数の経過した本は古本屋に持ち込んでも二束三文にしかならないことが多く、「せっかくなら社会貢献できるほうを」と寄付を選ぶひとも増えてきています。
古本の寄付は「団体が自ら絵本などを募集する」こともありますが、一般的にはNPOやNGOを取りまとめる仲介サイトを使った寄付が多いようです。
「古本 寄付」と調べるといろいろサイトが出てきますので、寄付したい団体と提携する、ご自身の環境に合わせたサービスを使うのが良いでしょう。
食品
活動内容でも紹介した「フードロス削減に取り組む団体」などへ、余った食品や飲料を寄付することもできます。集められた食品は、生活困窮する子どもや高齢者に支援されます。
フードバンクに寄付できる食品の種類、条件は団体により異なります。たとえば条件には、長期保存のきく食品(缶詰など)・賞味期限が◯ヶ月以上などがあります。
愛知県名古屋市でフードバンク活動をおこなう認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋では、次の条件にあてはまれば食品1つから寄付できます。
〈寄付できる食品〉
〈受付できない食品〉
|
本来なら食べる機会のない食品は初めから買うべきではないですが、どうしてもスーパーの安売り時に買いだめてしまう場合もありますよね。
昨今の値上げラッシュが原因で、フードバンクの食品供給も厳しくなっているとも言われています。食品ひとつが「人ひとりの命を救う」可能性もありますので、ぜひ対象品なら捨てる前に寄付も検討してみましょう。
〈送り先〉 事務所住所 |
ペットボトルキャップ
ペットボトルキャップを集めて寄付する方法もあります。「集めたボトルキャップを回収業者が買い取り、その買取金額の一部が寄付金になる」という仕組みです。ペットボトルキャップが2kgたまると、子どもたち用のワクチンが1人分できると言われています。
またペットボトルキャップはプラスチックのリサイクル資源に生まれ変わるため、正しく仕分けることはSDGsの取り組みにも繋がります。
プルタブ
プルタブとは、缶ジュースや缶ビールの飲み口を開ける際に、指をかけるつまみの部分です。胴に印刷の入ったアルミ缶よりも、プルタブのほうがリサイクルに適しているのです。集められたプルタブはリサイクル業者が回収し、その得た利益で「車椅子などの福祉に必要なもの」「発展途上国の難民支援活動」などで役立てられます。
もちろん1つ、2つでどうにかなる話ではありませんが、普段なら捨てるようなプルタブのリサイクルも意識してみてはいかがでしょうか。
なお少数の場合は、郵送を受け付けていない場合があるので注意しましょう。
ヘアドネーション
ヘアドネーションという言葉をご存じでしょうか。ヘアドネーションとは「髪の毛の寄付」です。寄付された髪の毛は、不慮の事故で髪の毛を失った人たちに向けたウィッグ作成のために使われます。
ヘアドネーションする方法は主に3つの方法があります。
- ヘアドネーション賛同美容室を利用する
- 普段行きつけの美容室に相談する
- 自分でカットして送る
最もスムーズで確実なのは、ヘアドネーション賛同美容室の利用です。正しくヘアドネーションカットができるほか、髪の毛の発送まで美容室がおこないます。
またヘアドネーションできる髪の毛は、通常31cm以上と言われています(15cm〜もあり)。引っ張ると切れてしまうほどのダメージでなければ受付は可能です。詳しくは各美容室に問い合わせましょう。
不用品
これまでさまざまな物品の寄付を紹介しましたが、日常生活で要らなくなった不用品をリサイクル・リユースとして寄付できます。不用品の寄付には、衣料品、ブランド品、カメラ、おもちゃ、ぬいぐるみ、楽器、雑貨(掃除用品・除菌関連・文具など)などがあります。
たとえば病気の子どもとその家族を支援する「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ(通称マックのお家)」では、食品・雑貨から家電製品まで幅広く物品支援を受け付けています。
〈提携する「DMHC名古屋ハウス」の場合〉 食品・・・紅茶・緑茶のティーバッグ、ドリップコーヒー、インスタント食品・レトルト食品、缶詰、お茶、お菓子、 日用品・・・名古屋市指定ゴミ袋(20L・45L)、BOXティッシュ、トイレットペーパー、ペーパータオル、掃除機用紙パック、 事務用品・・・未使用切手、テプラのテープ、ラミネートフィルム、コピー用紙(A4、A3)、色画用紙、乾電池(単3)、 |
不要品には「使う」「売る」「寄付する」「捨てる」の4つの選択肢がありますが、まだ使えるものはぜひ「捨てる」以外を選びたいものです。さらに「無駄なものを買わない」を意識すれば、ゴミ削減や発展途上国による安い賃金の労働を減らすことにも繋がります。
寄付できるものは各団体のホームページで確認できますので、不用品で寄付を始めたいという方はチェックしておきましょう。
【不用品で寄付する時の注意点】
不用品で寄付をするときは、かならず寄付先や現地の「供給状況」に目を通しておきましょう。
たとえば発展途上国のアフリカには、日本や欧米などから年間「20億着以上」の古着が届くと言われています。こうした古着は一着5円ほどで販売します。
一見、貧困国にとってはプラスしかないと感じるかもしれませんが、こうした善意の寄付は現地の産業をつぶしてしまう恐れもあるのです。
届いた衣服は「季節感」や「状態」もバラバラで、仕分けはすべて現地の人が時間やお金を使っておこないます。さらに支援で届いた古着をタダ同然で売るとなれば、繊維産業で安い賃金で働くひとたちを逆に苦しめてしまうのです。
何を必要としているか、近況アナウンスがホームページなどで報告されているのか、自ら責任をもって調べることが大切です。
お世話になった(なっている)場所から選ぶ
3つ目は学校、施設など「関わりや思い入れのある場所」から選ぶ方法です。ひとは誰しも生きてきた中でお世話になっている場所がありますから、そういった場所に感謝の気持ちとして寄付する方もいます。
団体以外で寄付できる場所は?
|
寄付できるものは、それぞれ寄付したい場所で異なります。たとえば図書館なら本の提供・ふるさと納税を使った寄付ですし、洋服店なら自社の古着などが対象です。また学校や自治体なら基本的に金銭のみの場合が多いでしょう。
関わりや思い入れのある場所を基準にした寄付には「実感を得られやすい」というメリットがあります。聞いたことがない場所、どこの誰かも分からない人へ寄付することに、少なからず抵抗を感じる方もいるでしょう。
自分と関わり深い場所なら安心感も違いますし、継続した寄付・社会貢献も期待できます。また昨今では「クラウドファンディング」の利用者も増えています。テレビやニュースなどで一度は見聞きしたこともあるでしょう。
クラウドファンディングとは「インターネットで企業または個人がサービスや商品などから思いを発信し、不特定多数の人から資金を供与する仕組み」です。「〜という思いからサービス(商品)〇〇を作りました」などとプロジェクトを立ち上げる起案者と、それに賛同する「支援者」から成り立ちます。
>>クラウドファンディングについて
寄付団体から選ぶ
4つ目が「寄付団体」から選ぶ方法です。寄付団体にも種類がありますので、それぞれ一つずつ解説していきます。
NPO
寄付先として最も有名なのが「NPO」です。
NPO(エヌピーオー)とは”Non Profit Organization”の略称で、意味は「非営利団体」です。日本NPOセンターでは「NPOは社会的な使命を達成することを目的にした組織」と定義されています。NPOの活動内容は、災害支援、子ども支援、貧困支援、高齢者・障害者支援など多岐に渡ります。
NPOには「NPO」「NPO法人」「認定NPO法人」と段階があります。NPOとNPO法人・認定NPO法人の違いは「法人格を持っているか」、またNPO法人と認定NPO法人の違いは「行政から厳しい審査をクリアしているか」を基準に判断します。
〈NPOの種類とレベル〉
|
かならずしも認定NPO法人を選ぶ必要はありませんが、NPOを選ぶ時の目安にしてみると良いでしょう。
NPOへの寄付は団体ホームページ、寄付団体の紹介サイト(モノドネからも可能)、通販サイトなどから可能で、中には切手やハガキも対象にした団体もあります。
NGO
NPOに似た言葉で「NGO」という団体も存在します。NGO(エヌジーオー)とは、”Non Governmental Organization”の略称で、意味は「非政府組織」です。
外務省では「貧困、飢餓、環境など、世界的な問題に対して取り組む市民団体」と定義されています。
国際連合(国連)がさまざまな協議をおこなう際に民間組織と政府組織の区別が必要となり、後発でNGOという略称が誕生しました。
NGOにも国内でおきている一部の問題に取り組む組織はありますが、あくまでも活動方針や理念は「世界規模の課題の解決」を軸とします。また、NPO同様に営利を目的としていません。
代表的なNGOとして「国境なき医師団」や「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(SCJ)」、また当サイトとも提携する「日本赤十字社」などがあります。2019年に死去した元ジャニーズ事務所社長の「ジャニー喜多川」さんは、この日本赤十字社に5億円を寄付し、その寄付金を基にジャニー基金も設立されています。
一般法人
一般社団法人や一般財団法人といった組織もあります。
これらの一般法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された法人で、NPOやNGOと同じく「非営利法人」です。
社団法人と財団法人の違いは「設立時の対象」です。社団法人は”人の集まりに法人格をあたえた組織”に対し、財団法人は立ち上げる人の財産に、法人格を与えた組織。財団法人の立ち上げには300万円以上の拠出金が必要です。
公益法人
さらに一般法人とは別に、公益社団法人および公益財団法人も存在します。
「一般」「公益」と寄付する側にとっては少々ややこしいのですが、公益法人とは「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて立ち上げた法人です。
一般法人と公益法人のおもな違いは「活動内容」です。公益法人は公益を目的とする事業をおこなう法人です。公益法人となるには一般法人の立ち上げが必要で、国や都道府県から認められて初めて公益法人となります。
つまり公益法人はNPO法人と認定NPO法人の違いと同様に、「ワンランク上の法人」と言えます。
NPO・NGO・一般法人・公益法人と紹介しましたが、違いを深く知る必要はありません。「こういった団体や組織があるのか」と広く理解しておくことが大切です。
また寄付団体を後に紹介した理由は、これまでの「目的」「寄付できるもの」「自分との関わり」「価値観」などを重要視していただきたい為です。
冒頭でも紹介したとおり、寄付は自発的な意志でおこなうものです。「誰かがしたから」ではなく、自分が「寄付したい」と思える団体をぜひ探してみてください。
モノドネでは不用品から寄付できる
さまざまな寄付の選び方を紹介してきましたが、じつは当サイト「モノドネ」からも寄付できます。「不用品を一度お金に変えて、その買取金額を希望の団体に寄付」できます。
モノドネではおもに下記のお品物が査定対象となります。
〈寄付できるもの〉
|
物品での寄付同様に、趣味の変わった衣料品、使わない家電やおもちゃ、昔コレクションしていたカメラ・骨董品などがあれば、ぜひ当寄付サービスもご利用ください。また査定はすべてモノドネを運営する「買取王国」の査定のプロがおこないます。
3.団体選びでは信用性・信頼性も大切
寄付するときに、寄付先の信用性・信頼性の確認はかかせません。せっかく寄付したお金が無駄にならないためにも、ご自身での下調べも大切です。下記で見るべき8つのポイントをまとめました。
ホームページ
インターネットが普及している昨今では、各寄付先の公式ホームページ運営は必須だといえるでしょう。YahooやGoogleなどから団体名で検索し、団体理念や団体組織が書かれているか確認します。
中にはまったく更新していないホームページも存在しますので注意してください。
活動報告
基本的に多くの寄付団体は、ホームページ内で直近の活動報告をします。理念や目的のための取り組みがなされているか、寄付金の使い道が何のために役立てられているかなど、内容も合わせて確認したいところです。また会計報告や年次報告などの公表も見逃せないポイントです。
SNS活動
現代は個人が当たり前のようにSNSを活用する時代です。SNSで活動内容をシェアしたり、外部とのコミュニケーションがおこなわれているか確認しましょう。団体・法人問わず、SNSの利用は、認知を高める効果もあります。更新頻度が高い場合は「活動に力を入れている」という一つの指標になります。
メディア掲載
テレビ・新聞・ラジオ・Webサイトなどのメディア掲載暦は、活動の信用性につながります。ただし設立して間もない団体などは、まだ掲載歴が少ない場合もあります。その場合は、団体トップのインタビューが公開されていないか、理事を含むメンバーの顔は公表されているか確認しましょう。
決済手段
決済手段とは「団体や法人に寄付するときの支払い方法」です。決済手段が重要な理由は「審査」です。たとえばクレジットカード決済を導入するには「加盟店審査」が必要です。これは「加盟店として十分な業歴、信用能力があるかが審査」されるものです。そのほかコンビニ決済、スマホ決済も同様に審査が必要です。
団体や企業との連携
団体・企業・メディアなどさまざまな組織との連携、または支援・寄贈実績がある場合、信頼性が高いといえるでしょう。これまでどういった組織と協働してきたのか、団体のホームページでも確認できます。なお、モノドネでも各団体様と提携をおこなっていますので参考にしてください。
>>モノドネと提携いただいている団体・法人
活動期間
活動期間も団体選びのひとつの目安にしましょう。できれば法人格を持ち3年以上が好ましいですが、これまで紹介した過去の実績やSNSなどを使った頻繁な活動報告がなされていれば1年でも2年でも問題ありません。ただし「認定NPO」はNPO法人立ち上げから1年以上経過していないと昇格できません。もしNPO法人と認定NPO法人で寄付を迷われる場合は、「税制優遇の有無」や「団体の理念・活動内容」など、ご自身の条件と照らし合わせて選ぶのがよいでしょう。
寄付者・寄付金の実績
過去に集まった寄付金、寄付者数は、上記でも紹介したNPO法人が国から認定を受けるための条件の一つです。実績判定期間中のすべての年で「3000円以上寄付した個人寄付者が100人以上」いなければ認定されません。ほかにも厳しい審査に合格する必要があるため、認定NPO法人は「課題解決に対する本気度が違う」ともいえるでしょう。
以上8つのポイントを紹介しました。すべてにおいて100点といった団体はそう多くありませんが、ぜひ寄付先を選ぶときの参考にしてください。
4.まとめ
本記事の「寄付先の選び方」をおさらいします。
|
初めて寄付する場合、これまで「寄付は怪しいもの」と認識していた方もいるかもしれません。寄付について調べると、従来の寄付先以外にもさまざまな方法があることを理解いただけたと思います。
もし身近に困っている人・施設があれば、手を差し伸べてみるのも良いでしょう。地域のボランティアに参加することも立派な寄付の一つです。一人ひとりできることは違いますから、焦らず自分のペースで寄付を進めていただければと思います。
モノドネでは、あなたの不用品を寄付金に変えることができる新しい仕組みです。
もう使わないけど捨てるにはもったいない。
そういったお品を寄付金に変えませんか?
手続きは3ステップ
-
寄付したい団体を選ぶ
モノドネ掲載団体の中から、あなたが応援したい活動団体を選びます。
-
申し込みをする
申し込みフォームに必要事項を入力し、完了メールを受け取る。
-
寄付品を発送する。
メールに記載された発送先へお品を発送する。
※買取王国系列店舗への持ち込みも可能です(一部対象外店舗あり)。
発送されたお品を専任スタッフが査定し、その査定額全額があなたの選んだ活動団体への寄付金になります。
査定額はメールにてお知らせします。
選んだ活動団体が寄付金控除対象団体であれば、寄付金控除を受けられます。

お品はそれを必要とする次の誰かにお繋ぎし、リユース・リサイクルされます
あなたにとっての不用品を、モノドネで社会に役立つお品に変えませんか?